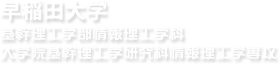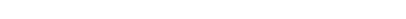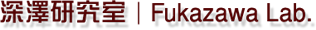サービス指向ソフトウェア
サービス指向ソフトウェアとは
近年、アプリケーションを構築するのに、サービス指向コンピューティングと言うアプローチが注目されている。 これは、新しくアプリケーションを作る際、ローカルに全ての機能を実装したり、ライブラリを用意するのではなく、Webサービスとして提供・公開されている機能をネットワーク越しに利用することで、新たなアプリケーション(Webサービス)を構築する手法である。 様々な企業や団体が、Webサービスを提供している現状では、企業が持つ膨大なデータを個人で利用できたり、保守などのコストを削減することができる。 既存の機能を利用することによってアプリケーションの構築が簡単になるだけでなく、複数のWebサービスを組み合わせることで、まったく新しいアプリケーションを構築することも可能になっている。
企業や団体の提供する機能を自身のアプリケーションに組み込み利用できるようになると、次は、Webサービスを利用した上で、如何に「より簡単に」、「より良い」アプリケーションを構築するかといった問題が取り上げられるようになる。 サービス指向コンピューティングの場合は、実世界に同業他社による競争があるのと同様に、部品となるWebサービスに複数の同種サービスが存在する。 当然、同じ機能であっても、利用できるデータ量の差や、サーバ等のハードウェアの性能差、場合によっては地理的な影響による遅延の差等が出てくる。 また、利用状況によっては、常に同じWebサービスを使用し続けるのではなく、Webサービスを切り替える方が、高い品質を得ることができるかもしれない。 同種の中でどのように選択をすれば、求めるアプリケーションをより高い品質で実現することができるのか、そして、どうすれば簡単にそれらのWebサービスを連携させたり、切り替えたりすることができるかを、ソフトウェア工学の知識・技術などと絡めて研究をしていくことが必要となる。