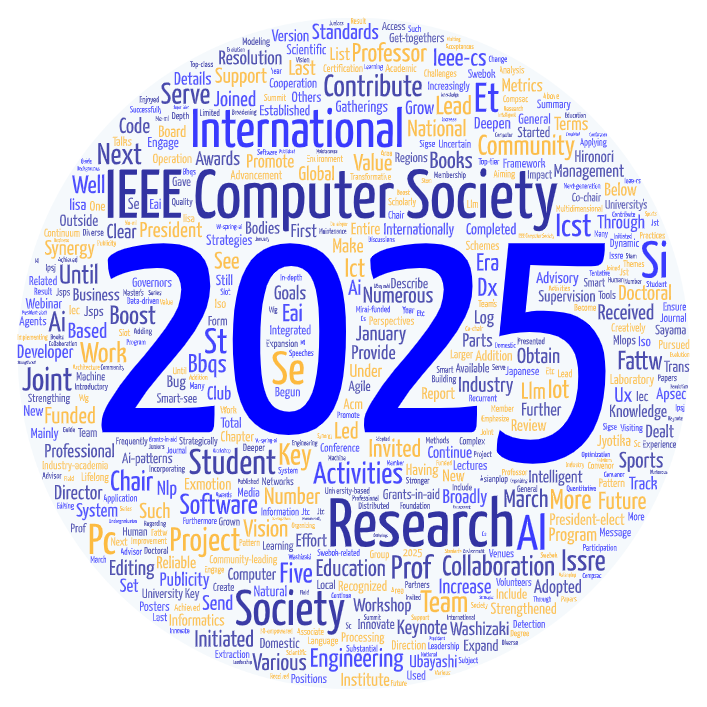2025年1月1日
2025年1月1日
鷲崎 弘宜
以下では、昨年の実績(2024年)を振り返り、新年の抱負(2025年)を「コミュニティ活動とプロフェッショナル貢献」「プロジェクト」「研究成果」「チーム編成」の観点から述べます。 英語版(English version)もあります。
- 2024年のまとめ: 国際進展の年
- 学会・コミュニティ: IEEE-CS次期会長、IPSJ SIGSE主査、ISO/IEC/JTC1/SC7/WG20 Convenor。IEEE COMPSAC/SIoTチェア、IISAチェア、FATTWチェア、AI-Patternsチェア、IEEE ISSREサポート、AsianPLoPサポート。SWEBOK Guide V4発行、IEEE CS Juniors program創設。ISO/IEC 24773シリーズ刊行完了。
- 研究教育プロジェクト: JSPS科研費MLパターン、JSPS 科研費 機械学習支援ソフトウェア保守進化(ME-ML)、JST未来社会eAIフレームワーク、スマートエスイー、K-12 STEM教育(狭山ほか、IEEE CS Juniors)など。さらに、5つ以上の産業支援プロジェクト。大学としての次世代AI分野博士育成W-SPRING-AI統括開始(JST BOOST採択)。
- 発信・業績: ジャーナル論文10+5本、国際会議・ワークショップ論文18本、書籍7冊(分担執筆、監修)、基調講演・招待講演24件、受賞13件。
- チーム: 鵜林教授が加わり研究指導体制の厚みと広がり。博士学生の増加。スポーツやBBQほか多数の集まりと懇親。
- 2025年のビジョン: 国際リードの年
- 学会・コミュニティ: IEEE-CS会長として会員エンゲージメント増強、産業界参画推進、AIイノベーションを含む技術領域リードの活動全体を推進および革新的発展(詳細: Leadership and Engagement: IEEE Computer Society 2025 Key Strategies )。IEEE SWEBOK Summit、IEEE Generative AI Innovation Summitほか新たな取り組み。IPSJ SIGSE主査(3月まで)、ISO/IEC/JTC1/SC7/WG20 Convenor。IEEE COMPSAC/SIoT、IEEE ICST、AsianPLoPの開催と貢献。SWEBOK関連推進。
- 研究・教育プロジェクト: JSPS科研費MLパターン、JSPS 科研費 機械学習支援ソフトウェア保守進化(ME-ML)、スマートエスイー、K-12 STEM教育など。さらに、5つ以上の産業支援プロジェクト。国際的な学会・コミュニティ活動との相乗効果。大学としてのAI分野博士育成W-SPRING-AI統括継続。
- 発信・実績: システム、ビジネス、社会のためのスマート・知的ソフトウェア工学において、国際的にコミュニティをリードする研究チームとして認知されるよう、産業界や国際的な連携を強化しつつ研究を幅広く推進し、より多くの資金を獲得し、また結果として、社会に多くの価値を提供し、知識体系に貢献する。
- チーム: 国内外連携の促進。留学生や博士学生の新加入を含む多様性。
1. コミュニティとプロフェッショナル貢献
2024: 鷲崎教授はIEEE Computer Society次期会長として、Jyotika会長のリーダーシップのもと、SWEBOK Guide V4の出版やWebinarシリーズを通じた展開、K-12に向けたCS Juniors Programの創設と様々な地域における実施、その他の専門的な活動など、IEEE Computer Societyの方向性をリードし、活動を推進しました。また、IPSJ SIGSE主査、ISO/IEC/JTC1/SC7/WG20 Convenorなど他の学会にも貢献し、国内外ソフトウェアエンジニアリングコミュニティのリードに努めるとともに、標準化についてシステムズ・ソフトウェアエンジニアリング領域の資格認証を扱うISO/IEC 24773シリーズの全パートの刊行を完了しました。エクスモーションやSI&Cの社外取締役・顧問ならび国立情報学研究所客員教授・人間環境大学 顧問を務め、産学連携や国内外連携を一層進めました。さらにFATTW 2024 Chair、IISA 2024 General Co-Chair、AI-Patterns Co-Chair, IEEE ISSRE 2024 Advisory Member、AsianPLoP 2024 Advisory Chair、COMPSAC/SIoT 2024 PC Chair、APSEC 2024 Education track Co-Chairなど多くの役職を歴任し、国際コミュニティをリード。
2025: 鷲崎教授はIEEE Computer Society会長として会員および社会へと明確にメッセージを発信し、会員エンゲージメント増強、産業界参画推進、AIイノベーションを含む技術領域リードをビジョンとして掲げます。理事会や数多くのボランティアの支援・参画を得ながら戦略的に活動全体をリードし、学会を成長および革新的に発展させ、人類社会へのコンピューティングを通じた貢献をますます高めます。詳しくは Leadership and Engagement: IEEE Computer Society 2025 Key Strategies をご覧ください。その中で新たな取り組みとしてはIEEE SWEBOK Summit、および、IEEE Generative AI Innovation Summitの開催を計画しています。また鷲崎教授はIPSJ SIGSE主査(3月まで)、ISO/IEC/JTC1/SC7/WG20 Convenorなど国内外学会や標準化活動を引き続きリードします。鷲崎教授はエクスモーションやSI&Cの社外取締役・顧問ならび国立情報学研究所客員教授・人間環境大学 顧問を引き続き務め、産学連携や国内外連携を一層進めます。さらに、AsianPLoP 2025 Conference Co-Chair、ICST 2025 Journal First Co-Chair、COMPSAC/SIoT 2024 PC Chairなど、国際コミュニティ醸成に務めます。
2. プロジェクト
2024: 10以上の研究・教育プロジェクトを成功裏に進め、その中には資金提供されたものや産業界が支援したもの、国際的な共同研究に基づくものが含まれています。また、大学としての次世代AI分野における博士人材育成プログラムW-SPRING-AIについてJST BOOSTに採択され、統括を開始しました。
2025: AI/LLM/機械学習/自然言語処理ほかをソフトウェア開発・運用に統合することで、ダイナミックで不確実な時代のシステム、ビジネス、社会のためのスマート・知的ソフトウェア工学を、主に国際共同研究、産業共同研究によって深化・拡大します。研究成果の学会活動への応用や、コミュニティにおける展望の研究活動への取入れ、コミュニティネットワークに基づく共同研究推進などにより、国際的な学会・コミュニティ活動との相乗効果を通じた国際展開に資する革新的・イノベーティブな研究・教育プロジェクトを推進します。
- 高信頼AI/LLMエンジニアリング・コンティニュアム(2020年~): JST未来社会事業eAIにおける高信頼機械学習システム開発運用のための多面的モデリングおよびパターン・MLOps統合エンジニアリング環境、および、その発展を通じた複雑かつ連続的な分散ソフトウェアシステム環境に向けたAI/LLMエージェントと人との協調エンジニアリング基盤
- JSPS科研費MLパターン プロジェクト(2023年~): 機械学習ソフトウェア工学パターンの抽出・検出・適用エンジニアリング
- JSPS科研費ME-ML(2021年~): データ駆動型NLP・MLソフトウェア保守・進化エンジニアリング
- スマートエスイー(2017年~): IoT・AI・DXのリカレント教育プログラム
- K-12 STEM教育(2015年~): ICTクラブ活動、プログラミング入門・AI・関連分野のワークショップなど
加えて、アジャイルメトリクスと開発者体験(Developer Experience)、ログ解析とUX改善、コードメトリクス、バグレポート処理、ナレッジマネジメント、標準化など、5つ以上の業界支援プロジェクトを実施していきます。また、大学としてのAI分野の博士人材育成プログラムW-SPRING-AIについて統括を継続します。
3. 発信・業績 (List of publications)
2024: 研究室として学生・メンバの研究進展や共同研究を通じて、論文誌・学術雑誌に10件の論文を掲載し(Future Generation Computer Systems, Software Quality Journal, IEEE Accessほか)、加えて5件の採択を得ました(ACM Trans. Architecture and Code Optimization, IEEE IT Professionalほか)。国際会議・国際ワークショップにおいて18件の論文・ポスター発表を行いました。書籍7冊について監修および分担執筆・寄稿しました(SWEBOK Guide V4.0ほか)。鷲崎教授は24件の基調・講演を行いました。活動は多くのニュースメディアで頻繁に報道されました。研究室として学生・メンバが計13の賞を受賞しました。昨年1月に掲げた目標はほぼ達成できましたが、2025年にはプロジェクトをより大きく、より深く、より国際化することで、よりインパクトのある、より社会と人類に貢献する活動を目指します。
2025: 国際的な学会・コミュニティ活動との相乗効果を発揮しながら、システム、ビジネス、社会のためのスマート・知的ソフトウェアエンジニアリングにおける国際的にコミュニティをリードするトップクラスの研究チームとして認知されるよう幅広く一層、創造的に研究を推進し、産業界や国際的な連携を強化しつつ、より多くの資金を獲得し、社会に多くの価値を提供し、知識体系に貢献できるよう取り組みます。手法、プラクティス、ツールなどの形で研究成果の多くを、ローカルおよびグローバルなパートナーを通じて、実質的な価値を生み出すために継続的に使用されるように取り組みます。成果発表について、論文数などの定量的な目標よりも、トップクラスの国際会議や論文誌、あるいは深い議論や共同研究につながる場を重視します。
4. チーム構成
2024: 鵜林教授が加わり研究指導体制の厚みを増し、研究チームとしてより強固なものとなるとともに、共同研究連携および研究テーマがより深く、より広がりました。また博士学生や留学生が増加し、多様性と層の厚みを増しました。1名が新たに博士学位を取得しました。スポーツやBBQほか多数の集まりと懇親機会を持ち、チームとして研究に限らず様々な活動を楽しみました。
2025: 国内外連携を促進するともに、留学生や博士学生の新加入を通じて研究チームとしての多様性をますます増していきます。私たちのチームは成長し、より多くの国籍、背景、考え方を持つようになりました。このような多様性は、上記のプロジェクトを推進するためのチームの創造性と、プロフェッショナル貢献に寄与しています。
- 2 教授, 1 客員教授, 1 客員准教授(予定、変更可能性あり)
- 5-7 博士院生
- 15+ 修士院生, 9+ 学部生
- 10+ プロジェクト研究生
- 招へい研究員を含む多数の連携・協力者