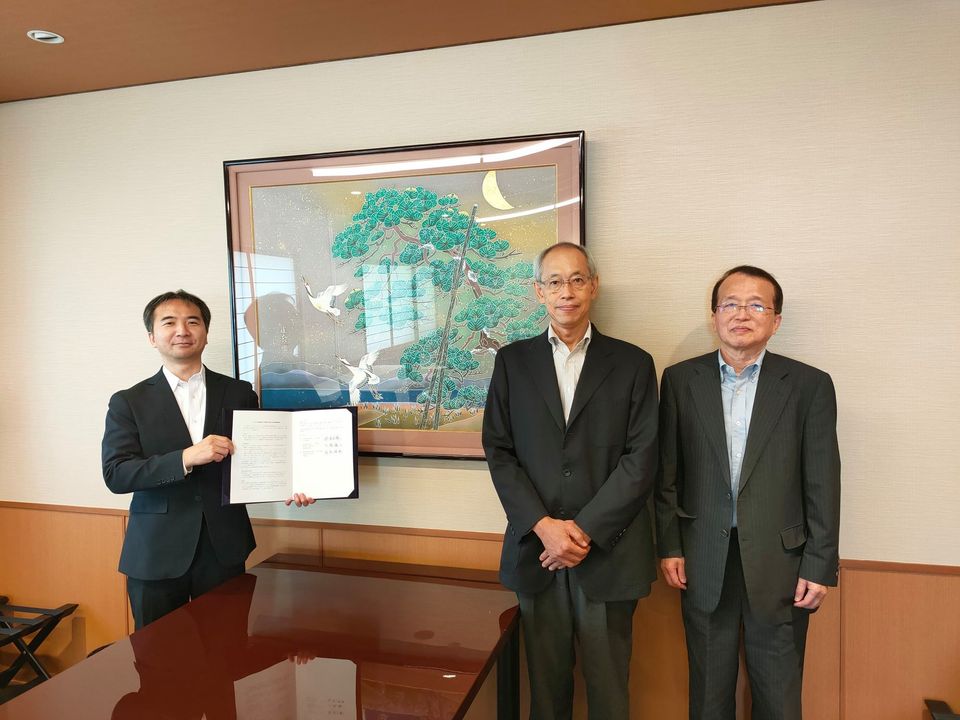Prof. Yoshioka together with Prof. Washizaki facilitated the group on patterns and pattern languages in Japanese at AsianPLoP 2020 from Sep 3 to Sep 4. All members had a great time to workshop nice patterns and pattern languages in various domains. Thanks to all authors and organizers!
カテゴリー別アーカイブ: 未分類
Prof. Washizaki gave a keynote titled Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns at AsianPLoP 2020
Prof. Washizaki gave a keynote titled Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns at AsianPLoP 2020 on Sep 3rd 2020.
- Hironori Washizaki, “Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns”, Keynote, AsianPLoP 2020: 9th Asian Conference on Pattern Languages of Programs, Sep 3rd, 2020.
スマートエスイーコンソーシアムの石川展開について石川県、コマツ、早稲田大学と協定締結
#SmartSE「スマートエスイーIoT/AI石川スクール」の開講のため協定を締結し、テレビや新聞などで多くの報道をいただきました。関係の皆様に厚く御礼申し上げます。昨年にもまして実践的なIoT・AI×ビジネスの社会人教育を展開してまいります。
- 読売新聞 地方版, IoTやAI人材育成へ 県がコマツ、早大と協定、2020/09/03
- MRO北陸放送, 石川県、コマツ、早稲田大 IoT人材育成など連携協定締結式, 2020/09/02
- 北陸中日新聞, AI技術者など育成「学校」開講 石川県、コマツ、早大 連携, 2020年9月3日
- 北國新聞, 石川から先端技術人材を石川県、コマツ、早大が協定締結, 2020年9月2日
- 毎日新聞, 高度人材育成へ協力 県とコマツ、早大が連携協定 /石川, 2020年9月3日 地方版
- NHK 石川, 産学官でデジタル技術の人材育成, 2020年09月03日
鷲崎教授がIIBA日本支部主催 ビジネスアナリシス サミット2020にて「スマートエスイー: 超スマート社会&DX時代のAI・IoT×ビジネスの人材育成と調査研究」と題し基調講演
鷲崎教授がIIBA日本支部主催 ビジネスアナリシス サミット2020にて「スマートエスイー: 超スマート社会&DX時代のAI・IoT×ビジネスの人材育成と調査研究」と題し基調講演。
鷲崎教授が IoTイノベーションチャレンジ2020にて「IoT時代のアーキテクチャ設計・評価」と題しセミナー講演
IoTイノベーションチャレンジ2020 昨年に引き続き 8/31午前に鷲崎教授が「IoT時代のアーキテクチャ設計・評価」と題しセミナー講演予定
Prof. Washizaki will give a keynote at AsianPLoP 2020
AsianPLoP 2020 program is out! Many great patterns and pattern languages to be workshoped. Prof. Washizaki wil give a keynote titled “Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns” on Sep 2-3.
ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2020 (SES2020)にてB3 飯島さん・新井さんがポスター発表予定
飯島 楓, 新井 珠旺, 津田 直彦, 鷲崎 弘宜, 深澤 良彰、”オープンソース開発における継続的インテグレーションの効果を発揮する条件”、ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2020 (SES2020)、ポスター、2020年9月10日~9月12日
日本デジタルゲーム学会 第9回 夏季研究発表大会にて B4 宅野君が発表予定
宅野勇輝ほか、”プログラミング的思考力育成ゲームにおける学習に効果的なゲーム要素の調査”、日本デジタルゲーム学会 第9回 夏季研究発表大会、2020年9月6日
デジタル教科書学会にてB4 矢島君が発表
矢島 理勢、斎藤 大輔、鷲崎 弘宜、深澤 良彰、大宮 秀利、小野寺 美咲、佐藤 衣津美、”プログラミング的思考評価のルーブリックの信頼性・妥当性の評価”、日本デジタル教科書学会(JSDT)第9回年次大会、2020/8/10-11
Practitioners’ insights on machine-learning software engineering design patterns: a preliminary study, accepted for ICSME 2020 Late Breaking Ideas track
Hironori Washizaki, Hironori Takeuchi, Foutse Khomh, Naotake Natori, Takuo Doi, Satoshi Okuda, “Practitioners’ insights on machine-learning software engineering design patterns: a preliminary study,” 36th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME 2020), Late Breaking Ideas track, Sep 26 – Oct 3, 2020.
Machine-learning (ML) software engineering design patterns encapsulate reusable solutions to commonly occurring problems within the given contexts of ML systems and software design. These ML patterns should help develop and maintain ML systems and software from the design perspective. However, to the best of our knowledge, there is no study on the practitioners’ insights on the use of ML patterns for design of their ML systems and software. Herein we report the preliminary results of a literature review and a questionnaire-based survey on ML system developers’ state-of-practices with concrete ML patterns.