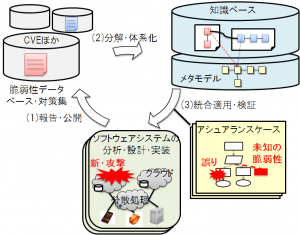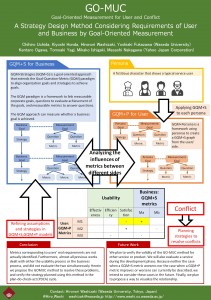Hidenori Nakai, Naohiko Tsuda, Kiyoshi Honda, Hironori Washizaki, and Yoshiaki Fukazawa, “Initial Framework for a Software Quality Evaluation based on ISO/IEC 25022 and ISO/IEC 25023,” Poster, The 2016 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability & Security (QRS 2016)(CORE Rank B), Vienna, Austria, August 1-3, 2016 (to appear)
Although the high quality of software is important for software stakeholders, quality of software products is not effectively defined. Some quality models have been proposed, but they cannot measure and evaluate software product quality comprehensively. Additionally, some companies define their own quality models. However, the quality measured and evaluated based on company-specified quality models cannot be compared to the quality of other software products. To alleviate this problem, ISO/IEC tried to define an international standard for comprehensive quality measurement and evaluation, but this standard includes ambiguous measurements, making it difficult to apply. Herein an initial comprehensive quality measurement framework, which includes a clear measurement plan based on ISO/IEC, is proposed. A case study confirms the usefulness of this framework. However, this framework should be revised to increase its effectiveness.